政治文書は社会科学の文献か?
元マルクス信徒
目次
はじめに
政治文書と学術論文の違い
「科学」、「科学的」と「真理性」は別
科学とは「諸科の学問」のこと
例えば、文学研究をどう見るか
政党の決定文書(政治文書)は学術論文ではない
科学(学問)には「学ぶ」、「問う」という二つの要素が不可欠
自画自賛に終始する「中間報告」
はじめに
志位和夫氏や田村智子氏らは、自分たちが作った大会決定や中央委員会総会決定等の政治文書を「社会科学の文献だ」などと言い、「科学だから学ばなくてはいけない」などと言う。※註(1)
※註(1)「私は、決定されるであろう中央委員会総会の決定というのは、社会科学の文献でもあるということを強調したいと思います。」「つまりそれは日本共産党の願望がただ書いてあるものではありません。世界と日本の現状を党綱領と科学的社会主義の立場で分析して、日本の進路、世界の進路を明らかにし、そのなかで党の役割を明らかにした文献が、中央委員会総会の決定なのです。それは党綱領と科学的社会主義に立脚し、集団的英知で練り上げられた社会科学の文献だということを強調したい。」
「ですから学ぶことが必要です。長いと言わずに――できるだけこれでも余分なことをはぶいて短くしたわけですので、学ぶことが必要です。」
<第28回大会第6回中央委員会総会結語(志位和夫)(2022年8月4日)>
同様のことは、2024年2月6日の全国都道府県委員長会議での田村智子委員長の問題提起、志位和夫議長の中間発言でも述べられた。
「今回の党大会決定は、非常に内容の充実したまさに歴史的決定であり、綱領路線をふまえ、それを発展させた社会科学の文献です。そして、全党の英知と実践を結集してつくりあげた集団的認識の到達でもあります。」(田村智子委員長の問題提起)
「こうした新しい理論的・政治的突破点の根本には科学的社会主義の理論があります。そして党綱領路線があります。ですから、田村委員長の問題提起で述べたように、今度の党大会決定は「綱領路線をふまえ、それを発展させた社会科学の文献」なのだということを、私も強調したいと思います。」
「そして、科学である以上は、学ばなくてはいけない。時間がかかってもそれを惜しまず最優先で学ばなくてはいけない、ということを強調したいと思います。同時に、学ぶことに全党が成功するならば、その科学的認識を全党が共有することになり、党の発展の確固たる質的土台をつくることになる、やりがいのある大きな事業なんだということをお互いに自覚してこの課題にとりくむことを呼びかけたいと思います。」(志位和夫議長の中間発言)
1.政治文書と学術論文の違い
政党の政治文書は、図書の分類からすると自然科学や人文科学ではないので、たしかに社会科学に入るだろう。しかしそれは、美術本や詩・小説等の文芸作品を含めた書籍や資料、記録文書、学術論文などをひっくるめて、分野別に便宜的に分けているだけであって、志位氏らの意図はそういうことではない。「科学だから学ばなくてはいけない」という言葉に表れている。大会決定文書という政治文書を、あたかも学術論文でもあるかのように思い込み、勘違いしているわけである。
学術論文の要件は、少なくとも、研究対象について先行研究(文献)を明示する、そして自説が現在の研究状況・学会の中でどのような位置にあるか、どの点に自説に独自性があるか、などを示す必要がある。そうすることによって、読者は、明示された先行研究や依拠した文献を参照することで、反論や反証をすることができ、討論や批判によって、さらに研究を深め、共通認識を高め、研究蓄積、研究水準を高めていく。学問研究はそうして研究対象について認識を高めていく。時間の制約もないし、多数決で結論を出したりはしない。
ところがマルクス主義の文化の影響下にある人々にとっては、共産党の大会決定や中央委員会総会、幹部会などの決定文書がそれだけで即「科学」であり、さらに「真理」でもあると思い込んでしまっているようなのだ。
共産党幹部の意図がどうであろうと、学問の世界では、政治文書で述べられている「主張」や「命題」、「政策」はあくまで研究の対象であり、論拠の検討や事実との照合がされて、その「真理性」が検証されるのであり、その検証作業や判定も簡単なことではない。
そもそも、自分たちの依って立つ理論を「科学的社会主義」などと自称するくらいなのだから、勘違いするのもやむを得ないとも言える。
2.「科学」、「科学的」と「真理性」は別物
しかし、「科学的」などという形容詞を軽々しくつけるものではない。自分たちの理論は「科学的」だと言ってしまえば、それ以外の理論は「非科学的」であると言っていることになるからだ。
そして、「科学的」と言えばその内容が即「真理」であるかのような錯覚も抱いてしまうのだ。科学上の命題は、真理である場合もあり、誤謬である場合も当然あるにもかかわらず、短絡的に「科学的」と言えば即「真理」「正しい」と見なしてしまうのだ。
このような「自分たちだけが真理を知っている」「おこがましさ」「うぬぼれ」「自画自賛」は、「前衛主義」「(大衆を)指導」「伝動ベルト」「外部注入主義」を生み出す。そればかりか、「真理の独占」「異端審問」「異論の排斥・弾圧」へと進んでいく。そう、旧ソ連などの現存した社会主義国のような恐るべき全体主義が導かれるのだ。※註(2)
※註(2)丸山敬一「社会主義は「科学」か-科学的社会主義論批判-」(社会思想史学会年報『社会思想史研究』通巻22号1998年北樹出版)参照。丸山敬一氏は、社会主義が科学を名乗ることの恐ろしさを、社会主義国家の人権抑圧の実態がこの帰結であるとして述べている。私も、エンゲルスが『空想から科学への社会主義の発展』で「社会主義は科学になった」として自分達の理論を「科学的社会主義」と自称したことは大いなる誤りだったと考えている。
「社会科学の文献であるから、学ぶことが必要です。」「科学である以上、学ばなくてはいけない。」とも言い、学ぶことによって「科学的認識を全党が共有する」ことを求めているわけである。
「科学である以上、学ばなくてはいけない。」
なるほどと、納得してしまいがちだが、そもそも「科学」についての捉え方に問題がある。科学とは何か?学問とは違うのか?
3.科学とは「諸科の学問」のこと
科学とは、諸々の科目に分かれた学問のことだ。諸科学、個別科学、個別学問である。学問が未発達な古い時代には、学問の対象が細分化されず、哲学がすべての分野の学問を網羅していた。時代が下って、個別の学問、諸科学が発達してきたのである。全体科学、全体学問としての哲学は、世界観や人生観という広い対象を扱う分野を担い、個々の分野については個別諸科学が担うことになる。
新しい知見を得るためには、研究対象を細かく限定する必要があり、そうすることによって実験や検証作業も可能になる。研究成果は学術誌に発表され、自由な討論や検証作業が行われる。そして真理性が確認され、知見が高まり、研究水準が上がっていく。こうして研究成果の実用化も進み、研究対象の細分化が進み、学問研究がさらに発展していくわけである。
しかし、科学を自然科学と同一視している人も多く、一般的、世間的にも、科学という用語は自然科学の意味で使用されることが多い。
確かに、自然科学の物理や化学などは、仮説を実験によって検証し、真理性を確かめるという一連のサイクルが短期間で行われ、正しさや間違いが誰にも明白なのに対して、対象が人間や人間社会である人文科学や社会科学分野の学問は、仮説を検証する実験作業が困難である場合が多く、真理性の判定が難しい。人によって見解がバラバラになっていることも多々ある。例えば、経済学にしても、労働価値説と限界効用価値説のどちらが正しいのか学派によって意見の相違があり、真理性の判定ができない、といった現状がある。
そういうわけで、「正しさ」や「真理性」が比較的短期間にハッキリと証明され、実用化されもし、生活に役立つことも明確な自然科学は別格の存在なのである。※註(3)
※註(3)ひとくちに自然科学といってもそう単純ではない。同じ自然科学でも、検証に時間を要し、真偽の判定に何十年もかかるものもある。例えば、人類学の分野では、近年、長い間謎であった新事実の発見があった。それは、現生人類である我々ホモ・サピエンスの遺伝子の中にネアンデルタール人由来の遺伝子が1~4%の割合で含まれているという研究結果だ。ネアンデルタール人だけでなくデニソワ人の遺伝子もメラネシアなどの現代人の遺伝子に含まれていることも明らかになってきており、ホモ・サピエンスと相互に交雑があった事実が示された。遺伝子の研究により、ネアンデルタール人やデニソワ人由来の遺伝子が現代人の健康に疫学的にどのような影響与えているのかも解明がされてきているようだ(篠田謙一『人類の起源 古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」』中公新書2022年)。化石からのDNA採取によって明らかになってきた化石人類の遺伝子研究にしても、成果が上がるのに時間を要した。
また、地質学のプレートテクトニクスの理論も学会で受容されるのに時間を要したらしい(泊次郎『プレートテクトニクスの拒絶と受容 戦後日本の地球科学史』東京大学出版会2008年)。
花粉アレルギー症状についての研究も、10年前に有力だった「コップ理論」は現在では「説明不足」だとされ、「シーソー理論」がそれに取って代わっているらしい。
このように、同じ自然科学の分野でも、真理性が分かるのに時間を要したり、有力な学説だったものが否定されたりすることがある。[註(3)終わり]
これに対して、自然科学以外の分野の学問は、研究者の数だけ学説があるように見受けられるし、何が正しいのか、真理なのか、いつまでたっても判然としない、白黒がはっきりしないという特徴がある。そのような学問分野を「科学」あるいは「科学的」などと呼ぶことを躊躇する気持ちもあるのだろう。しかし、元々科学とは諸科の学であり、諸々の科目に分かれた学問のことをいうのであって、自然科学だけを指すわけではない。
正しさや真理性の検証が簡単ではない自然科学以外の学問分野であっても、対象範囲を細分化し、条件を限定することによって、真理性を確定することは可能なのだ。
4.例えば、文学研究をどう見るか
自然科学的な明快さや「正しさ、真理性の検証」から遠そうな分野、例えば、詩歌・小説、文芸評論などを研究分野とする文学研究は科学とは言えないのだろうか?芸術は作品を鑑賞するだけなのか?
そんなことはない。作品が人に与える印象は、鑑賞する人によってまちまちだが、作品に込める作者の意図があり、作品が小説であれば、登場人物の人間関係や心理描写にリアリティがあるか、社会への風刺があるか、社会矛盾をえぐっているか、読者の共感を得ているか、物語の構成に工夫が凝らされ、物語の展開の続きに期待感が持てるか、結末の意外性や爽快感、悲壮感、等々、感想や批評の論点が限りなくある。作品に対する感想や評価は人によって千差万別だが、既に定着した作品評価、作家評価という一定の共通理解というものがあることも否定できない。
日本の近代文学史の概説書をひもとけば、明治大正昭和、そして戦後文学を含む150年にわたる多様で膨大な文芸の営みが紹介されている。そして、その時代の作家・作品が様々な流派、潮流に分類され、その特徴が示され、時代の変遷に従って配置されている。これはどの文学史の概説書も共通している。
つまり、様々な解釈があることも事実であるが、一定の定着した解釈・評価というものも存在するわけで(もちろん時代の変遷によって評価が変わりうることも事実であるが)、正しさや真理性が確定不能というわけではない。
5.政党の決定文書(政治文書)は学術論文ではない
そこで、①「大会決定、中央委員会総会の決定というのは、社会科学の文献である」、②「科学である以上、学ばなくてはいけない」という命題の検討に戻ろう。
まず①。
この命題は、図書の分類としては正しい。人文科学や自然科学の文献ではないから、社会科学の文献に分類されるため。しかしこの命題は、図書の分類として述べたものではない。「科学文献」つまり、学術研究論文の類いであると言いたいのだ。
しかし、中央委員会総会の決定文書は学術研究論文の要件を満たしているだろうか?学術研究論文は、少なくとも、研究対象の明確化、先行研究の明示、論拠となる文献の明示、が要件である。
ところが、「大会決定文書」や「中央委員会総会の決定文書」は明らかに要件が満たされていない。一方的に主張が述べられているだけで、読者が検証しようにも論拠が示されていないため、反証が不可能なのだ。
主張が事実と合致しているかを判断するための資料が公表されていない。判断材料を公表しないため、主張が正しいかどうか、読者には全く分からないのだ。
機関紙読者部数の日刊紙、日曜版のそれぞれの内訳が秘密のままなのだ。また、党員数にしてもしかり。年齢層別の党員数も曖昧なぼかした数字しか示していない。党員の増減数も、死亡者数を大会時に公表するだけで、離党者数、除名者数、除籍者数なども不明である。これでは、一般の党員や読者は、中央の報告が正しいかどうか判断できない。
6.科学(学問)には「学ぶ」、「問う」という二つの要素が不可欠
次に②。
科学(つまり学問)は学ぶ必要がある。これはその通りである。しかし、内容に対して疑問を持ったり反証を試みたりすることは想定されていない。
学問の学は、「まなぶ」。まなぶは、「まねぶ」さらに「まねる」から言葉が変容してきているらしい。まずは先人の知見を「まねる」ことから始めるわけである。まねることによって身につけるのだ。これも確かにその通りだ。
しかし、これだけでは学問は発展せず、知見は発展しない。学問の問、すなわち「問い」。「問う」ことが必要だ。志位氏らの言う「学ぶ」にはこの「問い」がない。疑問に思うことが学問の発展には必要なのに、これが抜けているのだ。疑問をいだかず、ひたすら決定文書の論理をなぞって覚えるまで「まねろ」、というわけだ。
疑問に思わず、ひたすら「まねる」「覚える」だけなら、技の訓練と同じだ。学問は学び問うことが必要なのに、志位氏の言う学習は学問ではないのだ。
志位氏らが「社会科学の文献だ」と誇る政治文書の内容が、いかに出鱈目の誤魔化しであるかをはじめに引用した同じ志位氏の「中間発言」から具体的に見てみよう。
7.自画自賛に終始する「中間報告」
「私たちは、これまで党員の現状をみるさいに、おもに、党員の現勢がどう推移したかで見ていくという傾向がありました。しかし、その角度からだけでは問題点がはっきりと見えてきません。角度を変えて、その年に新しい党員を何人増やしたかという目で見てみると、はっきりと弱点が浮かび上がってきました。それと、昨年の8月1日の現勢調査の結果をすべてつきあわせて、党建設部門のみなさんとも協議をかさね、さらに集団的検討を経て明らかにした答えが、大会のあいさつで述べた内容であります。これも初めての重要な解明となったと思います。」(2024年2月6日の全国都道府県委員長会議での志位和夫議長の「中間発言」)
なるほど、29回大会の「中央委員会を代表してのあいさつ」(志位氏)では、「10年ごとの年平均の新入党者数の推移」と、「党歴構成」が公表された。
「年平均の新入党者数」は、
1970年代は年3万人
1980年代は年1万5千人
1990年代は年6千人
2000年代は年1万1千人
2010年代は年8千人
であったといい、90年代が大きく落ち込んだ「空白の期間」だという。
そしてもう一つの「現勢調査で明らかになった党歴構成」では、
党歴0年~9年が、17,7%
党歴10年~19年が、14.0%
党歴20年~29年が、11.0%
党歴30年~39年が、8.0%
党歴40年~49年が、19.5%
党歴50年以上が、29.8%
だという。
このデータに加えて、「年齢構成」を一部公表している。しかしこれは、
「60代以上が多数を占めており、50代以下がガクンと落ち込んでいます。」
という大雑把な公表にとどまっている。これでは、党勢の詳しい実態は分からない。
28回大会から29回大会までの4年間のあいだに1万9千814人の党員が死亡したことを「開会のあいさつ」で公表している。新たに入党する人もあれば、死亡していく党員がいる。それだけでなく、「離党者(除籍、除名を含む)」も当然計算に入れなければならないが、こちらは公表していない。
だから限られた公表データを組み合わせて計算して現勢を推計しなければならない。共産党が判断材料となる詳しいデータを公表しないため、広原盛明氏※註(4)は、『赤旗日刊紙』に毎日掲載されている「党員死亡欄」の人数を根気よく計測され、党大会時公表の死亡者数と照らし合わせ、日刊紙に掲載されていない死亡者数の割合をはじき出し、それらを元に、「年平均の死亡者数」を推計されている。そして、公表される「新入党者数」、「年平均死亡者数」等から「年平均離党者数」を推計し、党員数の推移を示されている。とても面倒な作業をされているが、広原氏の作業のおかげで、我々外部の者でも共産党の公表する漠然とした数値よりも実態がよく分かるようになっている。詳しくは広原氏のサイトを見ていただきたい。※註(4)広原盛明のつれづれ日記https://hiroharablog.hatenablog.com/
党中央は、これらのデータは当然保持しているから、「60歳以上が多数」といった大雑把な構成ではなく、年齢別の党員構成の詳細を把握しているはずである。
しかし、詳しい年齢別の党員構成を公表しないのはなぜか?
おそらくそれを公表すると、一般党員のあいだに動揺がひろがり、従来と大して変わらない「党員拡大・機関誌拡大」方針ではとうてい改善不能であることが明らかとなってしまうからだろう。
「真実を恐れ」「真実を公表できない」人たちが党中央幹部なのだ。
これで、「今回の党大会決定ほど、多面的で豊かで充実した決定はそうはない、といっても過言ではない」「全党の英知と実践を結集してつくりあげた集団的認識の到達」などとよく言えたものだ。
第29回大会後1年3ヶ月経過したが、党勢は衰退するばかりである。機関紙読者数も約5万人減り、85万人から80万人へと後退していると推測される。党中央の方針(つまり大会決定や中央委員会総会決定)が破綻していることは、誰の目にも明らかである。
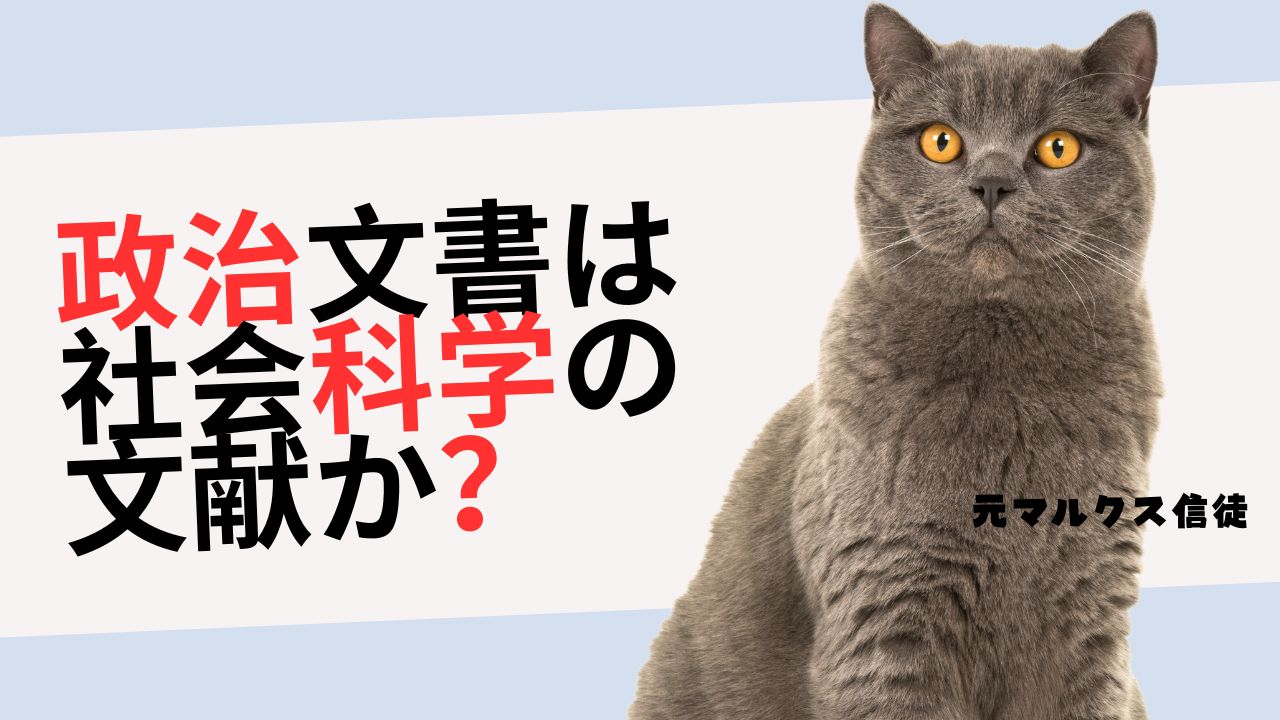

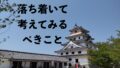
コメント