日本共産党ランキング
「しんぶん赤旗」が存亡の危機にあるが、党支持者にして将棋ファンとしては、将棋大会のことも心配になる。
囲碁・将棋 – 「しんぶん赤旗」(しんぶん赤旗HPより)
全国大会出場まで、参加者は地区大会⇒県大会、と、二段階の予選を戦わなければならない。予選の運営は地方組織にゆだねられているが、党員減、高齢化などで、地区委員会の負担が増している、ということはないのだろうか。地方議員にとっては市民との対話の場ともなるイベントではあるが、それなら、大会という形式にこだわることもない。楽しく将棋(+その他のゲーム)をプレイしながら(教わりながら)対話、地域によっては県単位の予選一度で代表決定、でもよいのではないか。
県大会を勝ち上がって、いよいよ全国大会である。党本部という立派な会場であるが、参加者のスマホ利用についてはどうなっているのだろうか。組織防衛の観点から、撮影・通信が制限されているのではないだろうか。それは仕方のないことではあるが、途中経過を外部に発信できないのでは、スマホによる発信の利点である速報性、臨場感、そういったものが生かせない。しんぶん赤旗公式アカウントで速報できないものだろうか。
大会の形式は、4人一組での予選リーグを行い、2勝した選手が決勝トーナメントを戦うという方式である。2敗で予選敗退となる。党本部という自前の会場で開催しているのだから、スイス式トーナメント(全員同じ回数の試合をして、勝ち数の順に順位をつける。高校生の全国大会では導入済み。結果を入力すると次の組み合わせを自動で作成してくれるアプリもたくさんある)など、前衛的な取り組みをしたらどうだろうか。選手にとっても、多くの強い相手と指す経験を重ねることができ、その経験を地元に持って帰れば、地域全体のレベルの向上ともなる。
詳細ページに「全国大会優勝者は新人王戦(プロ棋戦)の参加資格を得る」とあるが、このことにも大きな意味がある。
受験資格
・現在のプロ公式戦において、最も良いところから見て10勝以上、なおかつ6割5分以上の成績を収めたアマチュア・女流棋士の希望者
・四段以上の正会員の推薦のある者
勝ち進めば、プロ棋士編入試験の受験資格を得ることにもつながるのです。
仮に、日刊紙廃刊⇒将棋大会開催終了、となると、プロ棋士と対局する機会が減り、編入試験へのハードルが上がることにもなる。新人王戦についても、「奨励会三段が優勝した場合は三段リーグにおける次点一つを得る(三段リーグでの次点一つと合わせてプロ入り可能)」という特典がなくなり、プロへの道が少し狭められる。新たな引受先が現れたとしても、「しんぶん赤旗」は立派な文化振興事業を手放す、ということになるのではないか。継続していただきたいし、「終了やむなし」になったとしても、それは文化を守れなくなるほどの衰退を意味するのだ、と、共産党には認めていただきたいものである。
- 「将棋文化振興議員連盟」
国会内には議員によるこうした任意団体があって、共産党の議員も名を連ねていた。「いた」というのは、2024年に穀田恵二氏が引退したからである。総会が最後に開催されたのはどうやら2023年で、今年の参院選後に開催されるものと思われる。さて、2023年の総会で、他党の議員と羽生善治会長との間に実に興味深いやり取りがあった。
(日本将棋連盟HPより、一部抜粋)
・山本左近衆議院議員
将棋は日本の文化として残していかなければならない。
小中学校で地域に部活動移行していく中で、地域において部活動を支えるまた地域の中で将棋を指す人をしっかり増やしていけるような仕組みを進めていただきたい。
将棋は文化でもあるがスポーツの側面もある。スポーツ庁との関わりはどうなっているのか。スポーツ的な側面からも我々がバックアップできるようなことはないかと思っている。
(羽生善治・日本将棋連盟会長の回答)
文化とスポーツ
歴史的背景があり、海外の将棋はカテゴリーとして頭脳スポーツだが、日本の将棋は
家元制度の中で世襲されてきたことから伝統文化というカテゴリーで文化庁に担当いただいている。カテゴリーの問題だけで、スポーツ的な側面もあり、今後もスポーツの分野の方々との交流も行っていけたらと思う。
「将棋は文化であるがスポーツとしての側面もある」という点で、両者の見解は一致している。羽生会長からは補足のような形で「海外の将棋はカテゴリーとして頭脳スポーツ」という説明がなされている。事実、文藝春秋社刊行のスポーツ誌「Nunber」が将棋の特集を組んだりして、「将棋にはスポーツしての側面もある」という認識が浸透しつつあり、アジア競技大会でも、「棋類(囲碁・チェス・シャンチー)」が実施種目になっているのだ。(残念ながら、新日本スポーツ連盟の見解は「身体活動を伴わないものはスポーツとして認められない」であった。今でもそうなのだろうか。)山本議員の質問も、こういう状況を踏まえた上で、将棋に対する認識をアップロードしているものといえるだろう。新しい価値観。変わりゆく価値観。共産党はどれだけ対応できているだろうか?一部の党員、議員、幹部によるSNS上の発言を見るにつけ、十分に対応できているとは言えない、と思うのである。次の総会で参加する議員は誰になるのか?
将棋がナショナリズムに利用されるのは好ましくないし、共産党にはそうならないよう歯止めになってもらいたい。むしろ、共産党が掲げる多様性の尊重、異文化共生をも主張できるツールなのである。駒にはそれぞれ特性があり、長所短所がある。人も同じである、ずっと複雑であるが。日本とは別の国、別の文化の中で発達した「将棋のようなゲーム」に触れるもよし。
・おわりに
将棋は「理性」と「知性」が求められるゲームである。かつての共産党には、この二つに加えて「良心」があり、それが党としての強みでもあった。将棋において求められる「理性」と「知性」から導き出されるものには、他者へのリスペクトも含まれる。相手へのリスペクトによって対話は生まれるのではないか?実際「棋は対話なり」という言葉もある。愛国を声高に叫びながら他国や他民族を見下ろす人、それに大声で叫び返すだけの人、そこにリスペクトはあるだろうか。社会全体が失いつつあるのかもしれないが、共産党には「理性」と「知性」を取り戻してもらいたいものである。しんぶん赤旗の事業を通じて。共産党が抱える問題、課題を垣間見ることができた。最大の問題は「当の外から党の中を見ることができない」ことである。例えば党内で「将棋大会?あんなのは宮本顕治の負の遺産だ」という声があったとしても、外からは見えないのである。
最後にもう一言。赤旗と将棋のかかわりを語るうえで、全くこのことに触れないわけにはいかない。かつては赤旗記者の中にも、「奥山紅樹」という素晴らしい将棋ライターがいた。下里正樹氏である。除名されたことで、赤旗将棋欄への貢献も黙殺されてしまった。
虎次郎
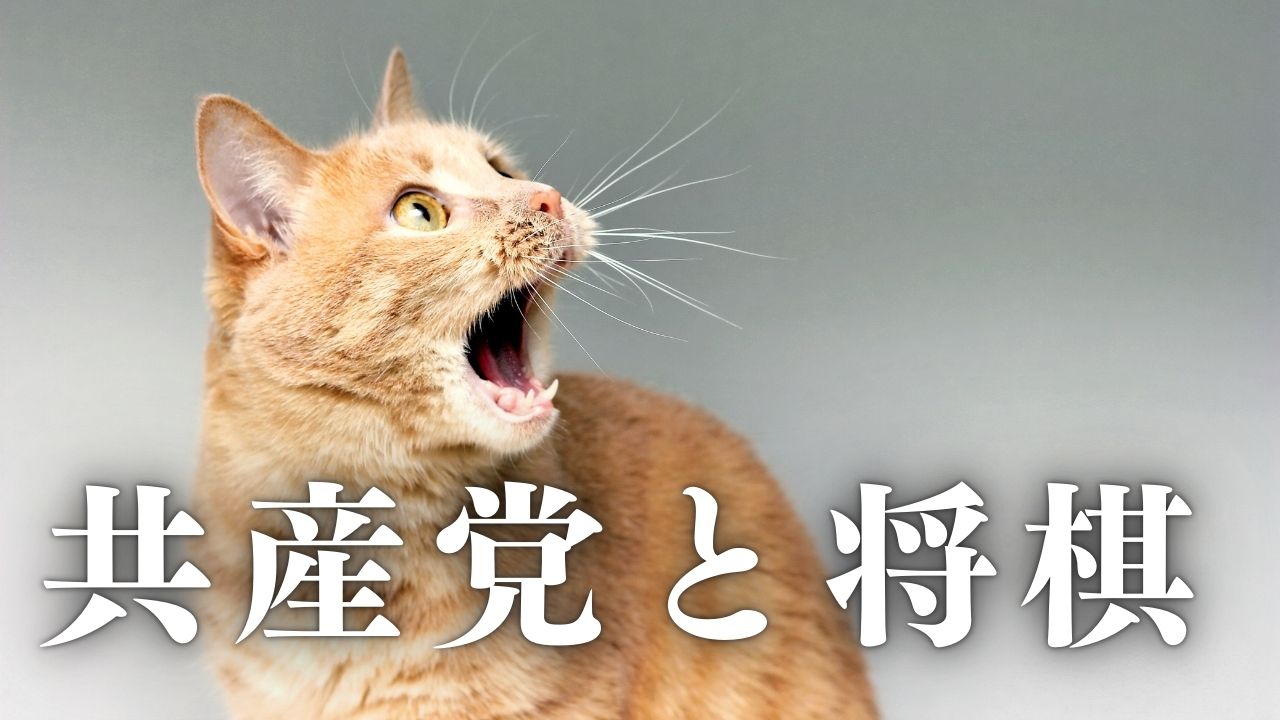
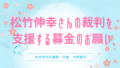

コメント